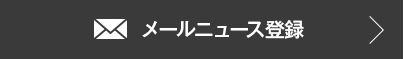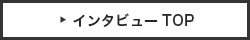インタビュー

2024年10月に白 承爀(ペク スンヒョク)氏をセンター長に迎えて大阪ビジネスセンターを新設。翌11月には、東京ビジネスセンターに「KOCCA CKL TOKYO」を併設しました。ここには韓国の多様なコンテンツ企業14社が入居しており、日韓ビジネスの新たな懸け橋となる施設として注目を集めています。2025年1月には、李 惠恩(イ ヘウン)氏が東京ビジネスセンター長として新たに就任。韓国と日本のコンテンツ産業のさらなる交流・協業を目指しています。
今回は、両センター長にそれぞれインタビューを行い、韓国コンテンツの最新動向や日韓のコンテンツ産業が直面する課題と将来の展望についてお話を伺います。
- 李 惠恩(イ ヘウン)氏(KOCCA[韓国コンテンツ振興院]東京ビジネスセンター センター長)[略歴]

新東京ビジネスセンター長 李 惠恩(イ ヘウン)氏の経歴と就任の背景
- ◆24年のKOCCAキャリアと東京センター長就任までの道のり
-
VIPO専務理事・事務局長 市井三衛(以下、市井) では、まずご経歴を簡単に教えていただけますか?
KOCCA(韓国コンテンツ振興院)東京ビジネスセンター センター長 李 惠恩(以下、李) 私は大学卒業してすぐにKOCCAに入社し、それから24年間勤務しております。東京センターへの赴任は、私にとって初めての海外勤務になります。
これまでKOCCAでは、多岐にわたる分野の業務を経験してきました。歴史を専攻していたこともあり、24年前に立ち上がった「歴史をデジタルコンテンツとして推進するプロジェクト」に初期メンバーとして参画しました。最も長く在籍したのは広報チームで、広報チーム長として機関長のPR業務を主に担当しました。
ほかにも、マンガやウェブトゥーンに関わったり、音楽・ファッションのチーム長を務めたりしてきました。近年は韓国の地域コンテンツに携わり、直近ではAIコンテンツを支援するチームに所属していました。
市井 センター長に就任されたときの気持ちや、その経緯についてお聞かせください。
李 任命された時期は、ちょうど海外勤務に挑戦してみたいと考えていた頃でした。現在、KOCCAは世界におよそ25か所の海外センターを展開しており、社内では比較的社歴の長いミドルマネジメント層が海外センターに派遣される流れがあります。
日本に特別な専門知識があったわけではありませんが、以前から日本のエンタメや放送コンテンツが好きで、よく観ていました。日本は韓国から地理的にも近く、文化的にも非常に身近に感じていました。赴任を決める際、両親を説得するときも「羅州(ナジュ:KOCCA本院所在地)からソウルに行くのと、日本からソウルに行くのは、それほど変わらない距離感だよ」と説明したほど、心理的な距離も近い存在でした。
市井 会社の方針とも合致し、日本のコンテンツにも親しみがあったことで、「日本で働けるのは良い経験になる」という前向きな気持ちで受け止められたということですね。
- ◆日本文化との出会い――安室奈美恵、岩井俊二、そして『スラムダンク』
-
市井 日本のコンテンツの中で、特に印象に残っているものは何でしょうか。
李 大学時代、日本のコンテンツをよく鑑賞していました。1997年より前です。岩井俊二監督の映画や小説、J-POP、とりわけ安室奈美恵さんをよく聴いていました。アニメでは『スラムダンク』が最も好きでした。
市井 なるほど。
李 入社当時、私が特に注力していたのは「韓国コンテンツをいかに発展させていくか」という点でした。そのため日本のコンテンツを研究対象として積極的に鑑賞し、多くを学びました。特に出版システムや連載の仕組みについて、ヒアリングやインタビューを重ねて把握し、マンガ産業全体を分析していました。
当時は「マンガこそが日本コンテンツ産業の根幹である」と考えており、それを参考に韓国でどう応用できるかを研究していたのです。同時に「韓国国内市場をしっかり育てなければ、コンテンツ産業は発展しない」という課題意識も強く持っていました。
それから20年以上が経ち、韓国のコンテンツはある程度成長を遂げたと思います。だからこそ「コンテンツがどのように海外において成長していくのかを現場で実際に体感したい」という思いが、今回、日本センター長を志願した大きな理由のひとつになっています。
市井 先ほど「1997年」に言及されましたが、それはKOCCAに入られる前ですか。
李 はい、学生時代です。その年に日本文化が開放されるという大きな政策があり、それを契機にコンテンツへの投資やデジタル化が進んでいきました。
私が日本映画を初めて観たのはそれ以前の1995年のことです。学校の前に「映画カフェ」という場所があり、そこでは映画好きの大学生に向けて日本映画が上映されていました。
当時、日本の映画やマンガが正規の形で広く公開・配信されることはほとんどなく、ごく一部を除いて、別のルートを通じて広まっていった作品が多かったのです。アニメや映画も同様で、『エヴァンゲリオン』をはじめ数多くの人気作が学生の間で楽しまれていました。
例えば、岩井俊二監督の『ラブレター』は韓国で最も知られている日本映画のひとつですが、実は劇場公開前からすでに多くの人が鑑賞していたので、2000年代初頭に正式公開された際の興行収入は控えめにとどまった、というエピソードもあります。
韓国コンテンツの国際展開と次のステージ
- ◆海外進出の成功と副作用
-
 市井 24年にわたりKOCCAで勤務され、韓国のコンテンツをより拡げていくことに携わってこられました。その中で成果を感じた部分、あるいは課題と感じた部分についてお聞かせいただけますか。
市井 24年にわたりKOCCAで勤務され、韓国のコンテンツをより拡げていくことに携わってこられました。その中で成果を感じた部分、あるいは課題と感じた部分についてお聞かせいただけますか。
李 成功しているジャンルとしては、まずK-POPや韓国ドラマが挙げられます。日本の政府関係者の方とお会いすると、「なぜ韓国コンテンツは世界で成功しているのか」と尋ねられることが多いですね。背景には、韓国国内の市場規模が小さいため、必然的に輸出に目を向けるしかなかった事情があります。
もちろん、日本のIPにも世界的に成功しているものは数多くあります。しかし企業単位で輸出額を比較すると、韓国が上回るケースも少なくありません。そうした意味では、韓国コンテンツは確かに大きな成果を挙げていると言えると思います。
一方で課題もあります。例えば日本は、新しいことに挑戦する際、何度も確認を重ねて慎重に進める印象があります。対して韓国はスピードを優先し、まず実行してから問題を解決していくスタイルです。 このようなやり方は、デジタル時代に迅速に適応できるという強みであると同時に、問題や試行錯誤を生み、成長の限界を招きかねないという弱点でもあります。
Netflixの普及により、韓国ドラマは一気に世界へ広がりました。これは大きな強みですが、同時に制作費の高騰という副作用も生みました。
例えば、世界的にヒットしたNetflixドラマ『お疲れ様』は、日常を描いた作品でありながら制作費は約600億ウォン(1話あたり約3.75億円)とされています。従来の韓国制作費とは桁違いで、こうした高額作品が市場全体の混乱を招く面があります。
その結果、制作本数は減少傾向にあり、今年は100本を下回る可能性も危惧されています。制作費が日本の5~10倍の費用がかかるため、制作会社が手を上げられないのが現状です。
外から見ると華やかに映る放送業界も、内側には厳しい現実が広がっています。これらは韓国コンテンツの強みと弱みを同時に象徴していると思います。
市井 ゲームやアニメといった分野ではいかがでしょうか。
李 ゲームは韓国の輸出産業の中でも大きな割合を占め、全体の約50%を担っています。オンラインゲームを中心に発展してきましたが、PCユーザー数には限界があり、中国との競争も激化しています。
日本の任天堂やソニーのコンソールゲーム市場は、韓国から見ると非常にうらやましい存在であり、近年は韓国政府もコンソール分野の育成に力を入れ始めています。
ウェブトゥーンは原作事業として好調ですが、制作スタジオ主導で企画が進むため、設定が重複してしまうことが課題です。これは日本のアニメ業界で「転生もの」がブームとなった時に似ています。
また、K-POP市場は大手4社が約80%を占め、アイドル中心で世界的な人気を誇ります。しかし、その一極集中は持続可能性に不安を残します。
KOCCAとしてはK-POP以外のジャンルの多様化を支援する方針です。日本の「J-POP100」のように、ロックなど多様なジャンルがランキングに並ぶ状況が理想ですが、現状の韓国市場はK-POPがほぼ独占しており、この偏りを是正することが大きな課題だと考えています。
- ◆中小企業を中心に――KOCCAの支援方針とその実際
-
市井 KOCCAの支援は大企業ではなく中小企業を中心にしている印象があります。この流れはいまも変わっていないのでしょうか。
李 資金面での支援は、いまも中小企業を中心に行っています。ただし、海外進出に関しては例外もあります。たとえばCJ ENMのような大手企業とのコラボといった特別なケースでは、大企業も対象となる場合があります。
VIPO事務局次長 槙田寿文(以下、槙田) ということは、プロモーションや国際的な取り組みの一部では大手を支援するケースもある、という理解でよろしいでしょうか。
李 その通りです。補助金など直接的な資金支援は中小企業が対象ですが、グローバル展開のプロモーション事業では、大企業やK-POPの4大事務所と組む例外的なケースも存在します。
CKL TOKYO:日韓コンテンツ産業連携の新たな拠点と構想
- ◆CKL TOKYOの第一歩
-
市井 CKLを設立し、現在14社が日本で活動を始めています。その成果や手応えについてはいかがでしょうか。
KOCCA CKL TOKYO(コンテンツコリアラボTOKYO)とは
 KOCCA東京ビジネスセンターに所属し、日本市場における韓国コンテンツ企業のビジネス展開を支援するために設立されたセンターです。2024年11月7日に正式開所し、日本企業との円滑な連携と市場へのアクセス強化を目的としています。
KOCCA東京ビジネスセンターに所属し、日本市場における韓国コンテンツ企業のビジネス展開を支援するために設立されたセンターです。2024年11月7日に正式開所し、日本企業との円滑な連携と市場へのアクセス強化を目的としています。
施設内には、ウェブトゥーン、ゲーム、放送、キャラクターなど多様なコンテンツ分野の韓国企業14社が入居しており、これらの企業と直接意見を交わし、アイデアを共有しながら相互協力を広げる場を提供しています。
李 これまでの20年間、東京ビジネスセンターの活動は、VIPOさんやDCAJさんと協力しながら、バイヤーを探して紹介することが中心でした。しかし現在は、そこからさらに一歩進めることを目指しています。そのためにCKLを設立しました。
日本での現地法人設立や支社化を通じて共同製作を進め、国籍を越えてコンテンツを共に作り出す。そうした方向へと支援の軸を移しているところです。
入居企業を選ぶ際には、日本の基本的なビジネスの進め方を理解しているか、そして本当に日本でビジネスを展開したい意思があるかを重視しています。
市井 実際の結果はいかがでしょうか。順調に進んでいるのでしょうか。
李 順調に進んでいる企業もありますが、試行錯誤を続けている企業もあります。
この7か月間、さまざまな取り組みをしてきましたが、まだ途上段階です。実際に法人を設立する段階になると、法務や税務の知識が不足しているケースが多く、東京センターとしてもまだまだ学ぶ必要があると感じています。
企業側も実務を十分に知らないまま来日している場合があり、試行錯誤を重ねています。たとえばスタートアップビザの取得に約6か月もかかるとは想定していませんでした。ビザがないと銀行口座が作れず、売上も立てられません。 そのため、実質的に各企業の本格的な事業展開が遅れてしまいました。
市井 手続き面の課題が大きく、事業内容を語れる段階には至っていないということですね。
李 そうです。一方で、いくつか大きな成功事例も生まれています。
たとえば映画制作会社JAYURO PICTURES ENTERTAINMENTはCKLの中でも成功している企業です。日本企業と強固に組んでいるわけではありませんが、CJ ENMと共同で日本のドラマ制作を手掛け、『私の夫と結婚して』をAmazon Primeで配信しました。
さらに日本の放送局と共同で次の作品も準備しています。
こうした事例は、日本の放送コンテンツに実際に参加しているという点で、CKL TOKYO設立の意義を象徴していると考えています。
また、ピンクフォンカンパニーは今年5月にTBSとMOU(基本合意書)を締結し、共同製作を進めています。この会社は、世界的にヒットした子ども向けアニメーションソング『ベイビーシャーク』を手掛けたことで知られている企業です。
さらに、デジタルアルバム制作会社NEMOZ LABも入居企業のひとつです。同社はNFCカードをスマートフォンで読み取ると音源が再生されるプラットフォームを開発し、韓国では累計500万枚以上を販売しています。
最近では、SMエンターテインメントのK-POPアルバムを日本でリリースしたり、日本企業やアーティストと共同でアルバム制作を進めたりしています。
- ◆海外企業が直面する制度の壁
-
市井 これまで支援を進めてこられる中で、日本の企業や業界に対して感じる課題や要望はありますか。
李 CKLの入居企業に限らず、スタートアップ投資を通じて世界から日本に進出する企業は確実に増えています。ただ、その流れと比べると、日本の行政手続きはまだグローバルのスピード感に追いついていない部分があると感じます。
例えば銀行口座の開設ひとつとっても、外国人にとっては非常にハードルが高い。海外企業が日本で売上を立てれば、日本法人としてGDPにも貢献するわけですから、もう少しオープンな制度にしていただけるとありがたいと思います。
日本政府もグローバル化やスタートアップ支援を進めていますが、やはり「速度感」が欠かせません。意思決定のプロセスも長く感じられます。
槙田 具体的にはどのような事例があるのでしょうか。
 李 パートナーとして日本で新しい取り組みを始める際には、まず委員会を立ち上げ、民間を含めて丁寧に合意形成を行うのが一般的です。そのため政策の実行までに時間がかかってしまうんです。
李 パートナーとして日本で新しい取り組みを始める際には、まず委員会を立ち上げ、民間を含めて丁寧に合意形成を行うのが一般的です。そのため政策の実行までに時間がかかってしまうんです。
もちろん、民間を巻き込みながら進めるのは大きなメリットですが、韓国の場合はリーダーシップを持った誰かが強く推進し、支援機関を立ち上げてすぐに実行に移すことができます。旗を掲げたら即行動、というスタイルです。日本ではそれが難しいのだと思います。
とはいえ、現在の韓国でももし新たにKOCCAのような支援機関を設立しようとしても、簡単にはいきません。昔に比べてシステムが複雑になり、日本と同じように時間がかかるのが現状です。ですから、日本における「時間のかかる仕組み」も理解できますし、ある意味では今の韓国も似た状況にあると言えるでしょう。
市井 よく分かりました。ありがとうございます。
李 日本の企業に対して特別な要望があるわけではありません。むしろ交流を深め、CKLに足を運んでいただき、取引ややり取りが増えることを望んでいます。
市井 その観点から、CKLをさらに広めるためのサポートについて、VIPOへの要望はありますか。
李 すでに多くのご支援をいただいています(笑)。
CKL TOKYOはKOCCAにとって世界で初めての海外拠点であり、政府予算を投じて設立された場所です。
そのため「早く成果を出さなければならない」というプレッシャーが常にあります。私たちも全力で取り組んでいますが、成果というのは契約件数といった数字だけではありません。広報活動や周囲からの評価など、さまざまな観点で成果を示す必要があります。VIPOにお願いしたいのは、CKLの魅力をより多くの人に伝える広報的な支援です。
- ◆新スローガン「NEXT K」が描く未来
-
李 韓国企業が日本に進出することは、場合によっては日本企業との競合と受け止められる可能性もあります。そこで私たちKOCCAが掲げているのが、新たなスローガン「NEXT K」です。
この「NEXT K」という考え方は、日本と韓国を別々に捉えるのではなく、パートナーとして共に歩むという発想です。つまり「Kコンテンツ」という枠を超えて、韓国と日本のコンテンツが一体となり、新しい作品を創り出していく――その役割をKOCCAとVIPOさんが担えればと考えています。
余談ですが、韓国政府は韓国企業の輸出拡大を大きな目標に掲げています。ただ、CKL入居企業が日本で売上を上げた場合、その売上は日本法人として計上されます。日本に優れた企業が一つ増えること自体を前向きに捉え、温かく見守っていただければと思っています。
市井 多くの方に知っていただくという意味では、今回のインタビュー記事は1万人以上に配信されますので、CKLをアピールするお役には少しは立てると思います。
槙田 CKLを日本企業にどのように利用してほしいとお考えですか。
李 CKLの大きな目標のひとつは、たとえ小規模でも、日本企業と韓国企業が交流できる場を定期的に作っていくことです。
「韓国企業とこんなことをしてみたい」「このテーマで企画したい」といったリクエストがあれば、ぜひいつでもお寄せください。「韓国のこの分野の企業を紹介してほしい」といったご相談でも構いません。
パートナーシップという形で一緒に取り組みたいというご要望があれば、ぜひご連絡いただきたいです。この拠点を積極的に活用していただけると、とてもうれしく思います。
市井 そうですね。
李 VIPOさんも、私たちと一緒にできることがありましたら、ぜひご提案ください。
日韓コンテンツ協業の次なるステージ
- ◆映像以外の分野へ広がる取り組み
-
槙田 放送やドラマ関連での日韓共同製作は多くありますが、それ以外の分野では具体的にどのような取り組みを考えていらっしゃいますか。
李 今年は「コリアスポットライト」というショーケースを予定しています。そこでは、日本と韓国の音楽関係者を招き、交流や意見交換を行うミュージックフォーラムのような場を設けたいと考えています。
もうひとつは、私自身が赴任前にAIチームのチーム長を務めていた経験を活かし、AIを用いて映像制作を行う若手クリエイターを招き、作品上映イベントを企画したいです。日本でも「コンテンツにAIをどう活用するか」は大きな課題ですので、実際にAIを活用している韓国企業の取り組みを紹介できる機会になればと思っています。
- ◆大阪ビジネスセンター設立の背景
-
市井 東京センターと大阪センターの役割の違いについて教えてください。関東と関西で地域的な棲み分けがあるのは想像できますが、二拠点に分けた目的は何でしょうか。
李 KOCCA本院としては、「関東と関西ではコンテンツ産業の特色が異なるのでは」という考えがあったのだと思います。ただ、実際に来てみると、デジタル化の進展もあり、そこまで明確な違いは感じません。大阪センター長も「どう役割を分けるべきか」については悩んでいるようですので、ぜひ本人にも聞いてみてください(笑)。
東京がビジネス全体を総括する役割を担うとすれば、大阪は韓国に地理的に近いため訪問者も多く、交流拠点としての強みがあります。
特にBtoC分野や、ビットサミットなどゲーム関連イベント、さらには任天堂をはじめとする関西拠点の存在を踏まえると、ゲーム分野は大阪が主導できれば理想的ですが、現状ではまだ試行錯誤の段階です。
- ◆ゲーム産業への支援と政策方針
-
槙田 KOCCAとして、インディーゲームへの対応はどのようにお考えですか。
李 インディーゲームについては「非常に大きな予算を投じている」というわけではありません。
韓国では「インディーゲーム」とは個人事業者による作品を指します。そのため、規模の小さい個人クリエイターへの支援はあまり行っていません。
KOCCAでは基本的に法人としての事業者を支援対象にしています。一方で、コンソールゲームの制作支援は行っています。
槙田 以前、ゲーム担当の方に伺ったとき「コンソールにもっと力を入れたい」とおっしゃっていました。その理由は何でしょうか。
李 政府のゲーム産業政策として、オンライン市場だけでは限界があるため、コンソール分野を強化する方針が示されています。そのため、コンソール開発の支援に重点が置かれるようになっています。
韓国映像産業の現在地と未来図
- ◆アニメーション産業支援の成功例
-
槙田 KOCCAとしてアニメーション分野の展望を伺いたいと思います。今後は「キッズスクリーン・サミット」のように子ども向けをさらに強化していくのか、それとももっと広い年齢ターゲットの市場の開拓を目指していくのでしょうか。
李 韓国アニメーションの支援は、これまで幼児・キッズ向け作品が中心です。劇場アニメなど年齢層を少しずつ引き上げる方向性もありますが、日本のように10代後半から大人までを対象とした大規模な市場は、まだ確立されていません。制作支援金によって企業が投資を受けられる仕組みはありますが、実質的にはキッズ向けが主流となっています。最近ではアニメ映画『退魔録』のようなヒットもありましたが、「市場が確立している」と言える状況ではありません。
槙田 例えば『ベイビーシャーク』で成功したピンクフォンカンパニーは、キッズスクリーン・サミットとも関係があるのでしょうか。あのサミットは、KOCCAが20年前からアメリカ進出を目指し、大規模なブースを設けてきた場です。日本では、ようやく7~8年前にVIPOが始めたばかりです。当初、韓国企業は下請け的な立場にありましたが、近年は共同製作やIP開発にも取り組むようになっています。ピンクフォンカンパニーも、その流れの一つなのでしょうか。
李 ピンクフォンカンパニーはアメリカとの共同製作をしていたわけではなく、初期からKOCCAの支援を受け、海外の見本市やキッズスクリーン・サミットなどに積極的に出展していました。その活動の中で生まれたキャラクターが大ヒットし、代表的な成功例となりました。
ピンクフォンカンパニーは韓国の一般的なアニメ制作企業とはアプローチが異なります。YouTubeに投稿された『ベイビーシャーク』の動画が数億回再生されるほどの爆発的ヒットとなり、キャラクターが商品化されました。その成功によって既存のIP「ピンクフォン」も注目され、アニメ化へとつながったのです。
- ◆制作現場が直面する構造的変化
-
槙田 今年のドラマ制作本数は100タイトル未満になるとのお話がありました(※2024年は約140タイトル)が、韓国映画の世界でも投資が十分に回らず、制作本数が減っていると聞いています。映画館の来場者数はピーク時の約60%まで減少し、資金が集まりにくくなっている一方、ドラマにはNetflixからの投資が多く入り、その影響で制作スタッフがドラマへと流れているとも聞きます。
ドラマ制作の現場では「配信用に莫大な制作費をかけるチーム」と「十分な予算を確保できないチーム」という二極化が進んでいると伺いました。予算を確保できないと結局は制作することができないため、結果的にこの構造がタイトル数の減少につながっているということでしょうか。
李 ご指摘の二極化がどの程度進んでいるか正確には分かりません。ただ、もしそうした状況があるとすれば、制作費が潤沢な作品の大きなメリットはキャスティング力にあります。現在、俳優のギャランティーは非常に高騰しており、一定規模以上の作品でなければ出演してもらえないのが実情です。
さらに、韓国ドラマの視聴者のリテラシーも高くなっており、一定以上のクオリティでなければ視聴されません。結果として、低予算の作品が成立しづらく、「二極化」というよりむしろ「制作費の少ない層がまったく存在しない」と言っても過言ではない状態だと感じています。
映画スタッフがドラマ制作に流れる動きもあります。映画のようなスケール感を持つドラマが増えてはいますが、映画の代替になるかといえば別問題です。映画産業の難しさは世界的な傾向であり、そもそも映画館に足を運ぶ観客自体が減っているため、劇場収益が確保しにくい現状があります。
 槙田 韓国の映画やドラマの持続可能性に懸念があるということでしょうか。映画には資金が集まらず、ドラマは制作費高騰で本数が140本から100本と3割も減少し、雇用も減ればスタッフの仕事も失われます。実際、日本の撮影監督協会には韓国から「雇ってほしい」という依頼が増えていると聞きます。
槙田 韓国の映画やドラマの持続可能性に懸念があるということでしょうか。映画には資金が集まらず、ドラマは制作費高騰で本数が140本から100本と3割も減少し、雇用も減ればスタッフの仕事も失われます。実際、日本の撮影監督協会には韓国から「雇ってほしい」という依頼が増えていると聞きます。
日韓共同製作が増えているのは、韓国側が日本の出資を得るために「一緒に作ろう」と動いているからではないかと考えていますが、この理解は正しいでしょうか。
李 それは私たちも懸念している部分です。そして、その理解は間違っていないと思います。
雇用の安定を両国間でどこまで実現できるかはまだ分かりません。ただ、最近CJやSLLといった韓国企業が日本の制作会社と組んで日本のドラマを手がけている最大の理由は、やはり制作費の問題だと考えています。現在の多くの共同製作は韓国の監督やプロデューサーに日本のスタッフを付ける形が多く、雇用安定の効果が十分に出ているかどうかは、現時点では判断が難しいです。
- ◆日韓共同製作に見る期待と課題
-
槙田 最近、日韓の共同製作に取り組んでいる企業を取材しています。先日、CJさんにお話を伺った際に感じたのは、単なるドラマ制作スタジオの枠を超え、「IPビジネス」という確固たる事業モデルを構築しようとしている点です。そのために日本を”テストベッド”として、さまざまな方法を試しているとのことでした。
一方で、日本企業にインタビューすると、「なぜ韓国企業と共同製作をするのか」という問いに、明確な答えを持つ方は多くありません。ただ、「韓国の企業と一緒にやってみたい」という雰囲気は確かに感じられます。
現在の環境では、韓国企業にとっては雇用の安定に直結しないまでも、制作費の高騰が続く中、日本で作るほうがコスト面で有利なことがあります。加えて新しいビジネスチャンスを開く可能性もあります。
一方、日本企業もグローバル展開を視野に入れ、「韓国企業と組んで力を借りたい」という思いがあるように感じます。双方のニーズが重なり合っていることが、共同製作の増加につながっていると、私たちは前向きに捉えています。
市井 韓国のPD(プロデューサーやディレクター)のもとで日本のスタッフが制作する場合、その作品は「韓国ドラマ」として扱われるのでしょうか。
李 いえ、日本のドラマです。キャスティングはすべて日本人が行っています。
市井 日本のテレビ局で放送される作品でも、監督が韓国人というケースがあるのですね。
グローバルで戦うという点では、日本より韓国のほうが進んでいると感じているテレビ局関係者は多く、その部分で学びたいことはたくさんあると思います。
李 確かに、日本のテレビ局の方がおっしゃる通り、韓国はグローバル展開において一歩先を行っている部分があります。ただ、実際に韓国から学べることがどれほどあるのかというと、正直なところ疑問もあります。というのも、そのように作られた作品であっても、まだ本当にグローバルで戦えるものは限られていると感じるからです。
「共同製作をすればうまくいく」と思われがちですが、実際にはそう単純ではありません。本来はお互いの不足している部分を補い合いながら進めるべきですが、現状ではむしろお互いの短所が目立ってしまうケースのほうが多いように思います。
市井 確かにその通りで、良い視点だと思います。「共同製作をすればすべてがうまくいく」などということはありえないと、やっと皆が理解し始めたのかもしれません。
では、そのうえで、どのような仕組みを作ればいいのかを考えていく必要がありますね。
李 まさに、その仕組みをどう作るかが、今一番悩んでいるところです。
韓国OTT産業のグローバルとローカル
- ◆グローバルOTT依存の現実
-
槙田 Netflixとの関係が深まると、制作や配信の仕組みも自然とNetflix方式に寄っていきますよね。最近では「グローバル化」という言葉が、単に世界規模のプラットフォームで配信されることを指してしまう懸念があります。
以前は海外の放送局に販売していましたが、今では「プラットフォームに売れば世界に配信され、収益も得られる」という考え方が強くなっているように思います。これで本当に「グローバル化」と言えるのでしょうか。KOCCAとしてはどのように考えていますか。
李 私たちもそこは悩んでいる部分です。短期的にはNetflixに販売すれば確かに売上は立ちます。しかし中期的に見たとき、それが本当に韓国コンテンツにとってプラスなのか、疑問は残ります。
韓国内のOTTプラットフォーム育成という観点からも政策的な支援はしていますが、それだけでは限界があります。一方で、Netflix中心の方向性をKOCCAが止めることもできません。
今KOCCAができるのは、制作会社の競争力を高め「グローバルOTTだけに依存しない」環境を整えることです。具体的には、制作会社がNetflix以外のOTTにもコンテンツを提供できるよう支援し、その力を育てていくことが重要だと考えています。
槙田 グローバルOTTそのものをコントロールすることはできませんよね。
李 その通りです。だからこそ、そうしたプラットフォームに販売できる力を制作会社が持てるよう支援しているのです。
槙田 Netflixに売れるのなら、他のOTTにも売れるはずですよね。つまり、グローバルOTTに対応できるようにプロダクションを育成し、どのプラットフォームにも販売できる体制をつくる、ということですね。
李 まさにその通りです。制作会社自身がIPを保有し、自分たちで流通の道筋を築けるような仕組みを目指して、私たちは支援を続けています。
- ◆ローカルOTT支援の仕組み
-
市井 ローカルOTTへの支援について、具体的に教えていただけますか。
李 基本は「OTT向けコンテンツの制作支援」です。ローカルOTTそのものに直接資金を出す制度はありません。その代わり、制作会社がローカルOTTと協業する場合、その制作会社が支援対象になります。
例えば、制作会社がローカルOTTと契約し、そのOTTのオリジナル作品としてファーストラン配信が決まった場合、契約書をもって支援金を申請できます。支援金は企画段階や契約締結後の一定フェーズで支給され、いわば「シードマネー」として機能しています。
槙田 つまり、ローカルOTTの強化を狙って、ローカルOTT向け配信作品に優先的に制作費支援を行っているという理解でよろしいでしょうか。
李:ローカルOTTに直接資金を出すことはできませんが、グローバルOTT依存を避けるために、ローカルOTTがオリジナルコンテンツを持って競争できるよう、制作会社を通じて間接的に支援しています。
槙田 ローカルOTTの育成は順調に進んでいますか。
李 はい、現時点ではうまくいっていると思います。
韓国では統廃合が進み、「wavve」「Watcha」「Coupang Play」「Tving」の4社ほどが残っています。
槙田 契約件数の状況についてはどうでしょうか。
李 詳細までは把握していませんが、いずれも有料サービスですので調べれば分かるはずです。
韓国にはAmazonがないため、「Coupang Play」がAmazonプライム・ビデオのような役割を果たしています。Coupangの配送サービス利用者は自動的にCoupang Playを視聴できるため、加入者数は最も多いでしょう。動画分野に全面的に注力しているわけではありませんが、認知度の高いオリジナル作品をいくつか保有しています。
市井 よく分かりました。
長時間にわたりインタビューにご協力いただきありがとうございました。
今後も引き続き交流を深めながら、双方のビジネスにおいて協力関係を築いていければと思います。ありがとうございました。


- 李惠恩(LEE, Hyeeun)
- 韓国コンテンツ振興院(KOCCA) 東京ビジネスセンター所長
- ソウル出身。
2000年梨花女子大学卒業、2002年梨花女子大学大学院修了。同年、韓国コンテンツ振興院の前身である韓国文化コンテンツ振興院に入社。文化原型デジタルコンテンツ事業、漫画、国際イベント開催などの業務を担当。
2009年の機構統合設立以降は、広報、音楽、ファッション、地域コンテンツなどの分野でマネージャーとして従事。
2025年1月より東京ビジネスセンター所長に就任
- ソウル出身。